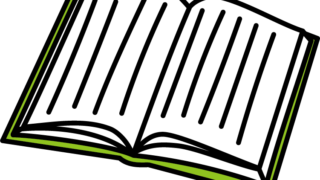離婚してバツイチになったとき、とても不安だったのを覚えています。
「この先ひとりでちゃんと生きていけるだろうか」
「このままひとりで迎える老後が心配・・・」
など将来に対する漠然とした不安で、怖くて、考えたくないと思う日もありました。
でも「不安」はきっと私ひとりだけの問題じゃないはず。
どうすれば「不安」がなくなるのでしょうか?
不安とうまく付き合うための4つの方法をお話しします。
「不安」とは何か?

そもそも「不安」とはなんでしょうか?
”不安(ふあん、英語: anxiety, uneasiness)とは、心配に思ったり、恐怖を感じたりすること。または恐怖とも期待ともつかない、何か漠然として気味の悪い心的状態や、よくないことが起こるのではないかという感覚(予期不安)である。”
引用:不安https://ja.wikipedia.org/wiki/不安
不安は「まだ起こっていない未来」に対して抱くもの。
「もしこうなったらどうしよう?」と、自分の頭で考え出したものを怖がることで、不安は生まれます。
「不安」と「恐怖」はとても似ているものです。
2018年の保健指標評価研究所の報告書では、パニック障害、強迫性障害、全般性不安障害(GAD)、社交不安のいずれかの形で不安に苦しむ人は、全世界で2億8400万人もいるとのこと。
これは世界人口の約3.6%にもあたる人数です。
「不安」は最も深刻なメンタルヘルス問題といえます。
不安になる要因
どういう時に人は不安を感じるのか?
不安を引きおこす重要な要素は、数十年前から変わっていないといいます。
- 友人関係
- 家族間の問題
- 職場の人間関係
- 失業
- 孤独
- お金 など
加えて現代では、SNSやスマホがあることによって、いろんなニュースが目に入ったり、フォロワー数やいいねの数といった、目でみて測られる幸せが重視されるようになっていることも、不安につながる要因になっています。
●「不安」は遺伝で受け継がれる
また、不安の傾向は遺伝によって受け継がれる、ということもわかっています。
遺伝的に「不安障害」をもつ人の40%は、同じような親戚がいるそう。
これは、ホルモンの値が遺伝子と密接な関係にある可能性があるからなんだとか。
たとえば、ネズミが果物のニオイを嗅いだ直後に、電気ショックを受けたとします。すると、ネズミはそのニオイをすぐに恐れるように。そして、もっと驚くことは、あとの世代のネズミたちもまた、一度も電気ショックにあったことがないのに果物のニオイを恐れるようになるでしょう。電気ショックの影響で、特定のニオイを嗅ぐことで過剰に反応するようになります。子孫たちも同じようにとても敏感になるのです。
引用:TABI LABOhttps://tabi-labo.com/284540/why-are-you-anxious
「不安」の引き金になるのは、たとえばパニック障害の場合、18歳から30代前半までのあいだに起こることが多いといいます。
このくらいの年は、人生における転機がたくさん起こる年頃で、親元を離れて自立するといった本来なら前向きな変化が、ある日突然、重圧に変わり不安を引き起こすことに。
不安を「治す」ことはできない
不安を感じると、どうにかしてこの不安な気持ちをなくそう、不安を治したい、と思うかもしれません。
しかし、そもそも不安というのは病気ではないので、「治す」ことはできません。
不安感が強くなると、より「治さなければいけない」という恐怖観念にとらわれて、それに依存するようになっていきます。
そのような執着がうまれると、自分がちゃんと「治っているか」確認したい、という考えに取り憑かれることにもなり、むしろ逆効果になってしまいます。
「明日スーパー行きたいけど、定休日じゃないよね?」なんて小さな不安から、「バツイチで1人で生きていくって決めたけど、将来年金は本当にもらえるのかな」という大きめな不安まで、「不安」というものは誰の人生にも普通にあるものです。
でもそれが極端になると、日常生活に支障をきたすことになります。
大切なのは、不安を「治す」のではなく「コントロール」することです。
不安をコントロールする方法

ではどうやったら不安をコントロールできるのでしょうか?
不安をコントロールして、うまく付き合っていきましょう。
1、「不安」を理解して受け入れる
不安な気持ちって、うまく説明できなかったり、モヤモヤしていて、あいまいな感情だったりします。
自分が何を不安に思っているか?を、自分に質問してみましょう。
質問することで、不安に思っている事柄を具体的に考えられます。
たとえば「離婚してバツイチになった」とした場合、自分が怖いと思う結果がなんなのかを具体的に考えます。
そして自分が何を心配しているか、自分と話し合うことです。

離婚してバツイチになってしまった!!
これからひとりで生きていけるのか不安・・・

離婚したけど、今現在ひとりでもちゃんと生きているよ。
何を不安に思っているの?

確かに・・・離婚したけど無事に生きてる・・・
これから先も私はひとりで生きていけるかな?

仕事もしているし、家族もいるし、友人もいる。
もし少しダメになっても支えはあるし、ひとりで寂しくなったらかまってくれる人はいるよ。
こんなふうに、漠然とした不安はさらに不安を呼ぶので、その前に具体的に考えてみることが大事です。
- なぜ不安に思うのか?
- 何を不安に思っているのか?
- それは今現在起こっているのか?
- 未来に起こる可能性がどのくらいあるのか?
順番に考えていくことで、自分の頭のなかが整理され、漠然とした不安ではなくなり、一旦落ち着くことができます。
考えが整理できれば冷静さを取り戻せるので、「バツイチになっても周りに家族や友人がいて支えてくれる」ため、ひとりじゃないと思うことができます。
そう思うことで不確実な未来への不安が和らぎます。
2、よく眠る
よく眠ることで、コルチゾールというストレスホルモンが減り、心が落ち着きやすくなり、立ち直りやすくなります。
睡眠不足はイライラや落ち込み、不安など、気分を変化させるトリガーになりますので、しっかり睡眠をとりましょう。
3、瞑想
瞑想は近年マインドフルネスともよばれ、メンタルヘルスの改善に効果的とされています。
不安感が強くなると、過呼吸になったり、概して呼吸のしかたが乱れがちに。
瞑想は呼吸を整えるので、それもいいんだとか。
不安は考えすぎによって引き起こされる場合もあるので、瞑想をして、意識的に考えない時間をつくることで、頭がスッキリする効果もあります。
4、エクササイズ
運動には不安感をとりのぞく効果があるとされています。
うつ病の人に治療の一環として運動がすすめられるように、体を動かして汗をかくことで気分が晴れ、不安の解消に役立ちます。
”運動をすることで、脳のストレスへの反応が弱まり、不安を感じにくくなることは、動物実験でも確認されている。 プリンストン大学の研究チームはマウスを使った実験で、運動によって、不安を制御する脳の領域が変化し、興奮を防ぐメカニズムが強化されることを突き止めた。
引用:保健指導リソースガイドhttp://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2014/003746.php
マウスを運動をする群としない群に分け、不安を制御する脳領域である腹側海馬にどのような変化が起こるかを調べた。
運動したマウスでは、興奮すると活発化するニューロンの反応が抑えられていた。さらにに、脳内の興奮性の神経伝達をコントロールする「GABA」(ガンマアミノ酪酸)がより多く放出されていることが判明した。
「生活スタイルや環境に合わせて、脳は柔軟に対応しています」と、研究者は説明している。不安という感情は、危険な状況を事前に避ける行動につながるが、過剰に働くと、現代人にとってメンタル面の健康を妨げる要因になる。
「運動は、脳が不安を引き起こす行動をコントロールする手助けになります。不安障害を抱える人にとっても、運動が効果的である可能性があります」と強調している。”
「不安」は生きるうえで必要なこと

不安な感情はネガティブに思われがちですが、私たちが生きるうえで必要な感情だったりもします。
不安に感じることがなければ、会社でプレゼン前に用意なんてしないし、受験勉強もしません。
間違えたらどうしよう、失敗したらどうしようという恐怖のおかげで、入念に準備するし、勉強します。
不安がなければ、車にひかれないように歩道を歩くこともしないかもしれません。
「不安」は私たちの身の安全を守り、向こうみずな行動をしないためのストッパーになってくれます。
私たちがものごとの前に立ち止まって考えるのは、不安があるからです。
そう考えると、不安に感じることは「慎重である」というポジティブな面もありますね。
不安は「直すべき弱み」ではなく、「利用すべき強み」として扱っていきましょう。
まとめ
「不安」はある種、生きていくのに必要な防衛本能で、なくすことは出来ません。
しかし、不安を理解してコントロールすることは出来ます。
不安はあなたの一部です。
不安に思う自分を否定するのではなく、受け入れることで理解して、うまく付き合っていければ、怖がる必要はありません。
人気記事離婚後の仕事探し【ママや主婦におすすめの求人サイト12選+職業別】