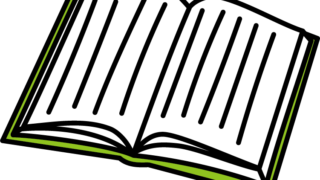夫と家庭内別居したいけど、子供もいるし生活が心配…
家庭内別居しても、今まで通り夫は生活費を払ってくれるの?
別居中の生活費はいくらくらいが相場なのか知りたい。
✔本記事の内容
- 家庭内別居中の生活費、相場はいくら?
- 婚姻費用の内訳
- 夫が生活費を支払ってくれなかったら
- 公正証書をつくっておこう
「夫婦関係が険悪で、夫と生活するのが辛い」
「離婚したいけど、仕事もパートだし今すぐはむずかしい」
「子供が成人するまで家庭内別居したいけど生活費はもらえるの?」
いろいろな理由から、離婚はしないけど家庭内別居を選ぶ夫婦はたくさんいます。でもその間の婚姻費用、生活費はちゃんともらえるの?と不安に思うこともありますよね。
本記事では、家庭内別居中に生活費はいくらもらえるのが相場なのか?を深掘りします。
家庭内別居中の生活費、相場はいくら?

夫婦間の生活費については、民法第760条にて、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する」と決められています。
婚姻費用はたとえ別居中でも、夫婦の生活に格差が出来ないように、夫婦が同じ水準で生活できるように設定されています。
法律で夫婦間には「扶養義務」があると決まっているので、家庭内別居しても生活費がもらえなくなることはありません。
生活費の算出方法はどうやって決まるか?
生活費がいくら払われるかは、夫婦で話し合っていくらにするか決めます。
夫婦間の話し合いで決まらなかった場合は、「家庭裁判所による調停」で決まります。
裁判所が出している養育費・婚姻費用算定表をもとに、夫婦の年収と子供がいる場合はそれを考慮して計算されます。
生活費の算出に必要な項目は?
調停で婚姻費用算定表をもとに生活費を計算する場合、以下の項目が判断材料として使われます。
たとえば、夫が会社員で年収600万円、妻がパートで年収100万円、子供なしだった場合、妻がもらえる生活費はおよそ8~10万円になります。
参考: 養育費・婚姻費用算定表 でそれぞれのケースが確認できます。
生活費算出に使われる年収は「手取り額」ではないので注意
ちなみに生活費を算出するさいに使われる年収は、手取り額ではありません。
児童扶養手当などをもらっている場合、それは子供のための社会保障なので年収には含まれません。
「家庭内別居」と「別居」では生活費の相場が変わる
同じ家のなかでおこなう「家庭内別居」と、実際に別々の家に住む「別居」だと、生活費の算出方法が変わります。
家庭内別居するさいの生活費については、裁判所が出している標準算定表をもとに、生活費を支払う側がすでに負担しているぶんを引いて計算される場合が多いそうです。
上記で「夫が年収600万円、妻が年収100万円、子供なしだった場合、妻がもらえる生活費はおよそ8~10万円」と例を出しましたが、 夫が住居費や光熱費などを支払っている場合、それが差し引かれます。
そのため一般的に家庭内別居したときに妻が受けとれる生活費は、実際に別居したときよりも少なくなることが予想されます。
婚姻費用の内訳は?何が含まれるの?

婚姻費用とは、生活に必要な費用全体を含んでいます。
婚姻費用には何が含まれるのか?内訳は以下のとおりです。
養育費は「公立の学校」に通っていることを基準とされているため、私立に通っている場合は別途請求できるケースがあります。
婚姻費用のなかには「交際費」や「娯楽費」も含まれます。人間として生活していくうえで、交際や娯楽は必要ですよね。
もちろん常識範囲外の高級品の購入費や、ギャンブルなどの娯楽は含まれません。
夫が生活費を支払ってくれなかったらどうする?

家庭内別居をすることになり、話し合っても夫が生活費を支払ってくれないときは、家庭裁判所で調停をおこない生活費を請求することが出来ます。
過去にさかのぼって請求することはできないため、支払ってくれない夫だったらすぐに手続きしましょう。
「どうすればいいかわからない…」という方はで法テラスが利用できる弁護士を無料で探してもらえます。
公正証書をつくっておこう

夫婦間の話し合いで話し合いがまとまっても、生活費をきちんと払ってくれない心配がある場合は、公正証書をつくっておくと安心です。
公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。
公正証書には証明力と執行力があります。
たとえば婚姻費用の支払いについて公正証書をつくっていて、支払いが滞った場合、本当なら裁判をして確定判決を受けなければおこなうことが出来ない、給与や口座の差し押さえなどの「強制執行」の申し立てがすぐにおこなえるので、支払いがストップするのを防ぐことが出来ます。
公正証書を作成するには
公正証書の作成手順は以下のとおりです。
①内容を決める
夫婦間で「生活費をどちらが支払うか」「毎月の婚姻費用は○○円にする」「いつまでに支払う」など、公正証書にする内容を話し合って決めます。
決めた内容はおたがいに分かるように書き出しておきます。
②公証役場へ行く
夫婦で決めた内容を公証役場にもっていきます。
公証役場は全国約300か所あり、どこの公証役場でも受け付けてもらえます。
参考:全国の公証役場一覧
必要なもの
③内容を確認する
公証役場に内容を提出したら、その後、その内容を公正証書にした原案が送られてくるので、間違いないか内容を確認します。
もし間違いがあればこの時に訂正します。
④公正証書を取りに行く
公正証書が出来ましたよ、と連絡が来るので、夫婦そろって公証役場に取りに行きます。
公正証書の内容を確認したら、署名捺印します。
公正証書の原本は公証役場に保管され、夫婦それぞれには謄本が渡されます。
必要なもの
公正証書作成の手数料
公正証書を作成するさいの手数料は法律で定められています。
婚姻費用の支払いに関する公正証書の場合は、10年分の合計金額をもとに手数料が決まります。
| (合計金額) | (手数料) |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 11000円 |
| 1000万円まで | 17000円 |
| 3000万円まで | 23000円 |
| 5000万円まで | 29000円 |
| 1億円まで | 43000円 |
たとえば月10万円婚姻費用を支払う内容だった場合は、10年分で1200万円になるので、公正証書作成手数料は「23000円」になります。
その他の手数料
そのほかにも用紙代・切手代などの雑費がかかることがあります。
記載する内容によってかかる金額が違いますので、お近くの公証役場に問い合わせてみてください。
自分で手続きができないときは
公正証書は自分たちで手続きすることも可能ですが、もし「この金額は妥当なの?」「どうも内容が不利な気がする」など不安があったりうまくまとめられないときには、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するのがベターです。
家庭内別居のとき、夫婦関係がこじれてうまく話し合いがすすまない、相手が話し合いに応じてくれないなどの状況になることは普通です。
専門家に間に入ってもらうことでスムーズにすすむことが出来ます。
では無料で日本全国から法律の専門家を紹介してくれるので利用してみるといいと思います。
関連記事>>日本法規情報の評判と口コミ【失敗しない離婚に強い弁護士を選ぶ方法】