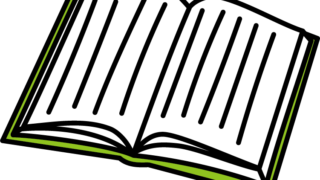夫婦関係がうまくいっていないから家庭内別居をしたいけど、どうやって始めたらいいの?
同じ屋根の下で暮らしてるわけだし、ルールとか決めたほうがいいのかな?
✔本記事の内容
- 家庭内別居で決めるべきルール11個【実体験からおすすめ】
- 【体験談】私が元夫と決めた家庭内別居のルール
本格的に別居したり離婚する前に、多くの夫婦が通る「家庭内別居」。
パートナーがいなくてもやっていけるかどうかのお試し期間のようなものです。
でも家庭内別居ってどう始めているのか?気になりますよね。
本記事では実際に家庭内別居をした経験から、家庭内別居のルールについて紹介します。
家庭内別居で決めるべきルール11個【実体験からおすすめ】

家庭内別居するのにルールは必須!
ズバリ家庭内別居を続けていきたいなら、ルールは必要です。
パートナーとは同じ家にいるので、ルールを決めておかないと、あやふやな部分が多く必要以上に顔を合わせてストレスになったり、困ることが起こります。
家庭内別居を続けていくうちに、だんだん自然とルールができてきますが、はじめに決めておくことでおたがいが納得できるので、よけいな問題をうまなくてすむメリットがあります。
とくに子供がいる家庭では、夫婦同意のもと家庭内別居をする場合、子供が混乱しないようにルールを設けておくことが重要です。
家庭内別居とは?の記事はこちらから↓
家庭内別居で決めるべきルール11個
①共有部分の使用について
●リビングルーム
リビングルームは、最もパートナーと顔を合わせる機会が多い場所です。
私は必要以上に元夫と顔を合わせるのが嫌で、できるだけ近寄らないようにしていました。
でも部屋の構造上、リビングを通らないといけない場合もありますよね。
もしどうしても顔を合わせたくないのであれば、リビングの使用時間を決めておくことです。その時間以外はリビングに入らない、と決めておけば、ムダにストレスを感じなくてすみますよ。
●お風呂
お風呂に入ろうとして、パートナーが長風呂しているとイラっとするもの。
元夫はお風呂につかるのが好きで、2時間とか入っていたので、使いたい時間がかぶったときは相当イライラしました。
だいたいでいいので、お互いが使用する時間をはっきりさせておくと便利です。
●キッチン
男性はあまりキッチンで料理することが少ないかもしれませんが、キッチンに冷蔵庫があるので、あんがい頻繁に顔を合わせる場所になります。
個々の部屋に小さい冷蔵庫があれば、必要以上に顔を合わせる心配が減るかも。
②生活費用について
家賃・光熱費・生活費などの支払いをどうするか、あらかじめ決めておきましょう。
家庭内別居後も、夫婦には「扶養義務」がありますので、生活費がもらえなくなることはありません。
関連記事>>家庭内別居中の生活費はいくらもらえるのが相場?
ただし、家賃や光熱費の支払いは家庭内別居するまえと一緒で、食費などの生活費だけは個々で負担する夫婦も多いようです。
私は家庭内別居後も、ふたり分の食事をつくっていたので、生活費も夫が出していました。自分の交際費や交通費なんかは、自分のパート代でまかなっていました。
生活費は支払い履歴がのこる振り込みがおすすめです。
金額や、いつまでに振り込むかなど決めておきましょう。
③食事について

家庭内別居後、夫に食事をつくるかつくらないかは、それぞれ分かれるところ。
元夫はまったく料理ができない人だったため、私は食事の用意だけはするように決めました。一緒に食べることはしませんでしたが。
夫は料理ができないけど作りたくない!という場合は、無理につくらなくてOK。外食や買ってくるなど手はあります。
お互い自分の分を料理する場合は、冷蔵庫の食材を区別するなどの工夫が必要になります。
もし夫に食事をつくってほしいと頼まれて、「家庭内別居しているのに、自分だけが料理を担当するのは不公平」と感じる場合は、ほかの家事を夫に担当させましょう。
お互いが家事を担当することで、公平さがうまれ、ストレスなく家庭内別居がスムーズになりますよ。
④洗濯について
洗濯機はだいたい共有になりますよね。
洗濯は別々という夫婦が多いと思いますが、洗濯ものを干して乾かす時間も考えて、洗濯機を使う日を決めておくと便利です。
⑤掃除について
個々の部屋は自分で掃除するとしても、リビングやトイレ、玄関などの共有部分の掃除についても決めておきましょう。
そのくらい気がついたほうがやればいい、と思っていても、たいていどちらかばかりが掃除するはめになってストレスになることが。
⑥連絡手段について
保険の手続きや子供の行事など、パートナーと連絡をしないといけないときもあります。
用事だけ冷静に伝えるためには、メールやLINEがおすすめ。
履歴が残るので、言った言わないなどの不必要なケンカも避けられます。
⑦顔を合わせたときについて
お互い顔を合わせないように時間帯をずらして生活していても、ときどき会うことがあります。
同じ家にいるので、避けられないことですよね。
気まずいですが、あいさつくらいはしたほうがいいでしょう。
無視していると、より顔を合わせることがストレスになりますし、子供がいる場合は親の態度を見て「嫌いな人は無視してもいい」と学んでしまう危険性があります。
近所の人、くらいの割り切った意識で接すれば、家庭内別居も快適に過ごせます。
⑧休日の過ごし方
お互いの休日がかぶって家にいると、顔を合わせるリスクも多くなります。
土日がお休みなら、土曜は妻が外出して、日曜は夫が外出する、などのルールを設ければ、お互い休日を過ごしやすくなります。
関連記事>>家庭内別居中の休日の過ごし方【ストレスなく過ごすために】
ちなみに私はインドア派、元夫はアウトドア派だったため、休日はだいたい元夫は家にいなかったので、快適に過ごせました。
食事も休日はつくらないと決めていましたよ。
⑨子どもについて
家庭内別居することで、子どもにあたえる影響を考えるかたは多いのではないでしょうか?
子どもは5歳にもなれば、お母さんとお父さんの仲が悪いことくらいわかってしまいます。
家庭内別居していれば、最近一緒にいないな、と気づかれてしまい、「どうして一緒にいないの?」と質問されることもあるでしょう。
両親の不仲は子どもに関係ありません。
パートナーと顔を合わせたくないばかりに、子どもの運動会へ参加しない、などは、子どもが両親から受ける愛情をじゅうぶんに感じられない場合があり、子どものその後の人格形成に影響します。
子供の自己肯定感は「育つ環境」によってどんどん低くなっていくことが分かっています。
関連記事>>あなたの自己肯定感が低い原因10個【今すぐ高める方法】
また、子どもを使って会話するなど、子どもを巻き込むのはやめましょう。
子どもにとって、母親も父親も両方大切な親です。その親から板挟みにされる子どもの気持ちを考えましょう。
関連記事>>家庭内別居が子供に与える影響は?ストレスだけじゃない!
⑩実家との付き合いについて
正月やお盆など、実家や親せきづきあいが増えるシーズンは、家庭内別居している身としては憂鬱な時期です。
私は自分の実家へは、夫とは家庭内別居状態であることを伝えていましたが、夫の実家にはいっさい不仲だといっていなかったので、がまんして仮面夫婦をよそおっていました。
どうしても夫とは一緒に行きたくない!というかたは、イベント事がないときに夫の実家にひとりで行っておくと、正月に行かないことがあってもごまかせるかも?
関連記事:
⑪将来について
離婚せずにずっと家庭内別居を続けていく場合、「将来についてどうするか」もどこかのタイミングで話し合っておく必要があります。
家庭内別居するくらいですから、もはや赤の他人と思っている方もいるでしょう。
すぐに必要ではないことかもしれませんが、おたがい独り身だと思って、自分の最後は自分で手続きしておくほうが問題が少なくなるかもしれません。
家庭内別居でルールを作る理由
家庭内別居といっても、夫婦が同じ家に住んでいる以上は、完全にパートナーを自分の生活から切り離せないですよね。
家庭内別居をすると、相手とのコミュニケーションがほぼなくなるので、ざっくりとでも決めておけば、相手の行動が予測できて、対応がしやすくなります。
お互いの生活リズムが分かっていれば、その時間を避けながら生活できます。
例えば「夫は夜10時に帰ってくるから、その前にお風呂や歯磨きをすませて部屋に引っ込もう」とかですね。
あらかじめルールを決めて、極力相手とかかわらないように、円満な家庭内別居ライフを送りましょう。
【体験談】私が元夫と決めた家庭内別居のルール

私は元夫と、3年間の結婚生活のうち、1年~1年半くらい家庭内別居していました。
私は元夫からほとんど放置されていたので、3年家庭内別居だったといえば、そうかもしれません。
私が元夫と家庭内別居だ!と思い、決めたルールはこちら↓
- 平日の食事は私が担当、休日はつくらない
- 食事をつくるかわりに、生活費は夫がだす
- 平日、私が起きている時間には、夫は帰らない
- 夫が帰るまえまでに就寝準備を終わらせて部屋に引っ込むようにする
- 洗濯は別々
- 掃除は私が担当
- 休日は夫が外に出かけるが、出かけない日は私が外出する
夫が家にいないことが大半だったので、ざっくりとルールを設けました。
基本的に夫が生活費を出していたので、やれる家事は私が担当することに。でも洗濯ものはパンツなどさわりたくないので、別々にしました。
家庭内別居はおたがいがストレスを減らして生活したいからするものなので、自分がしたくないことははっきりと主張しておきましょう。
家庭内別居は割り切ることが大事

家庭内別居は、顔を見たくない相手から距離をおくことで、精神的にストレスをへらすことができます。
そのためには割り切ることが大事です。
せっかく家庭内別居したのに、相手の物音にイラついていたら、もったいないです。
家事や育児を「仕事」として考えて、夫には生活費という名の「給料」を払ってもらうと考えましょう。
それ以外については自由で、なにをしていても一切干渉をしないようにすれば、同居人としてストレスなく、円満な家庭内別居ライフが送れます。
人気記事離婚後の仕事探し【ママや主婦におすすめの求人サイト12選+職業別】